スマホに押され、世の中のコンデジ(コンパクトデジタルカメラ)は非常に少なくなりました。
普段はスマホ、画質を優先する時はミラーレスカメラ。
コンデジは絶滅の危機に瀕しています。
一方で、コンデジにはコンデジにしかない魅力があります。
それは、ミラーレスカメラよりも軽量コンパクトでありながら、スマホよりも優れた画質を確保している点。
小さくて、軽くて、よく写る。
それを体現化しているのが、コンデジです。
私のメインカメラはソニーのα9ですが、ソニーのCyber-shot RX100m7も併用しています。
どういった時に、コンデジを使用しているのでしょうか?
- ミラーレスカメラのサブとして使用
- 旅行で荷物を減らしたい時
- 大きいカメラを出す事がはばかられる時(カフェなど)
メインのカメラとして、ミラーレスのサブカメラとして、TPOをわきまえる際にも。
色々な使い方があります。
コンデジ、1台あると本当に便利ですよ。
具体的にどんなコンデジがオススメなの?失敗せずに選びたい。という人も多いと思います。
そこで、日頃からコンデジを活用している私が、2024年のおすすめコンデジを紹介したいと思います。
まずは、結論から述べておきましょう。
- ソニー Cyber-shot RX100m7
- ソニー Cyber-shot RX100m5a
- キヤノン PowerShot G7X mark3
- OM SYSTEM(旧オリンパス) TG-7
- リコー GRIII
- リコー GRIIIx
なぜ、上記コンデジがおすすめなのか、順番に解説していきます。
その前に、おすすめカメラの所有経験、主な使用コンデジを紹介しておきます。
同機種
- ソニー Cyber-shot RX100m7
- リコー GRIII
1世代前
- ソニー Cyber-shot RX100m5(RX100m5のマイナーチェンジ前)
- キヤノン PowerShot G7X mark2(G7X mark3の前機種)
- オリンパス(OM SYSTEM ) TG-6(TG-7の前機種)
- ソニー Cyber-shot RX100m7
- ソニー RX0II
- キヤノン PowerShot G1X mark3
- オリンパス(OM SYSTEM ) TG-6
最新のおすすめコンデジの記事はこちら。
おすすめコンデジの選定基準
おすすめコンデジの選定基準について説明します。
選定条件は3つ。
- コンパクト
- スマホカメラとの差別化ができる
- 新品購入できるカメラ
順番に解説していきます。
①コンパクトであること
1つ目の条件はコンパクトであること。
一眼レフやミラーレスカメラは、画質は優秀なものの、大きく重い。
対して、コンデジは小型軽量に重点を置いて開発されたものが多く、携帯性に優れています。
今回は、質量300g台までのコンデジに限定して選びました。
②スマホカメラとの差別化ができること
最も携帯性に優れているのは、スマホのカメラ。
スマホカメラと同じ画質や機能では、意味がありません。
そのため、スマホカメラとの差別化ができるカメラを選定しました。
- ズームができる
- 圧倒的な画質
- 耐衝撃性
- 並外れたオートフォーカス性能
③新品購入できるカメラであること
どんなに優れたカメラでも、買えないのでは意味がない。
2024年2月現在で、新品購入できるカメラに限定して選びました。
おすすめカメラの性能|スペック
まずは、カメラの性能を見ていきましょう。
おすすめコンデジとして選定したカメラは6つ。
- ソニー Cyber-shot RX100m7
- ソニー Cyber-shot RX100m5a
- キヤノン PowerShot G7X mark3
- OM SYSTEM(旧オリンパス) TG-7
- リコー GRIII
- リコー GRIIIx
スペック比較
| RX100m7 | RX100m5a | G7X mark3 | TG-7 | GRIII | GRIIIx | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | ソニー | ソニー | キヤノン | OM SYSTEM | リコー | リコー |
| センサーサイズ | 1インチ | 1インチ | 1インチ | 1/2.3インチ | APS-C | APS-C |
| 有効画素数 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 | 約1200万画素 | 約2424万画素 | 約2424万画素 |
| レンズ 35mm換算 | 24-200mm F2.8-4.5 | 24-70mm F1.8-2.8 | 24-100mm F1.8-2.8 | 25-100mm F2-4.9 | 28mm F2.8 | 40mm F2.8 |
| ズーム | 8.3倍 | 2.9倍 | 4.2倍 | 4倍 | ||
| ファインダー | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
| 内蔵フラッシュ | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 手ぶれ補正 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 自撮り | 180°チルト | 180°チルト | 180°チルト | |||
| タッチパネル | あり | なし | あり | なし | あり | あり |
| スマホ連携 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| USB充電 | microUSB | microUSB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 低速限界設定 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| RAW記録 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 質量 (バッテリーSD含む) | 約302g | 約299g | 約304g | 約249g | 約257g | 約262g |
| サイズ | 約102×58×43mm | 約102×58×41mm | 約105×61×41mm | 約114×66×33mm | 約109×62×33mm | 約109×62×35mm |
| 価格 | 約16.5万円 | 約11.1万円 | ※販売中止中 | 約6.2万円 | 約12.0万円 ※受注一時停止 | 約12.6万円 ※受注一時停止 |
2024年3月現在、キヤノンのG7X mark3は販売中止中です。
ディスコンではないので、比較対象に入れています。
2024年3月8日にリコーイメージング株式会社から、GRIIIおよびGRIIIxの受注一時停止が発表されました。
コンデジの性能を見える化
おすすめコンデジの性能を見える化しました。
下図を見れば、何となくカメラの性能が見えてくるのではないでしょうか。
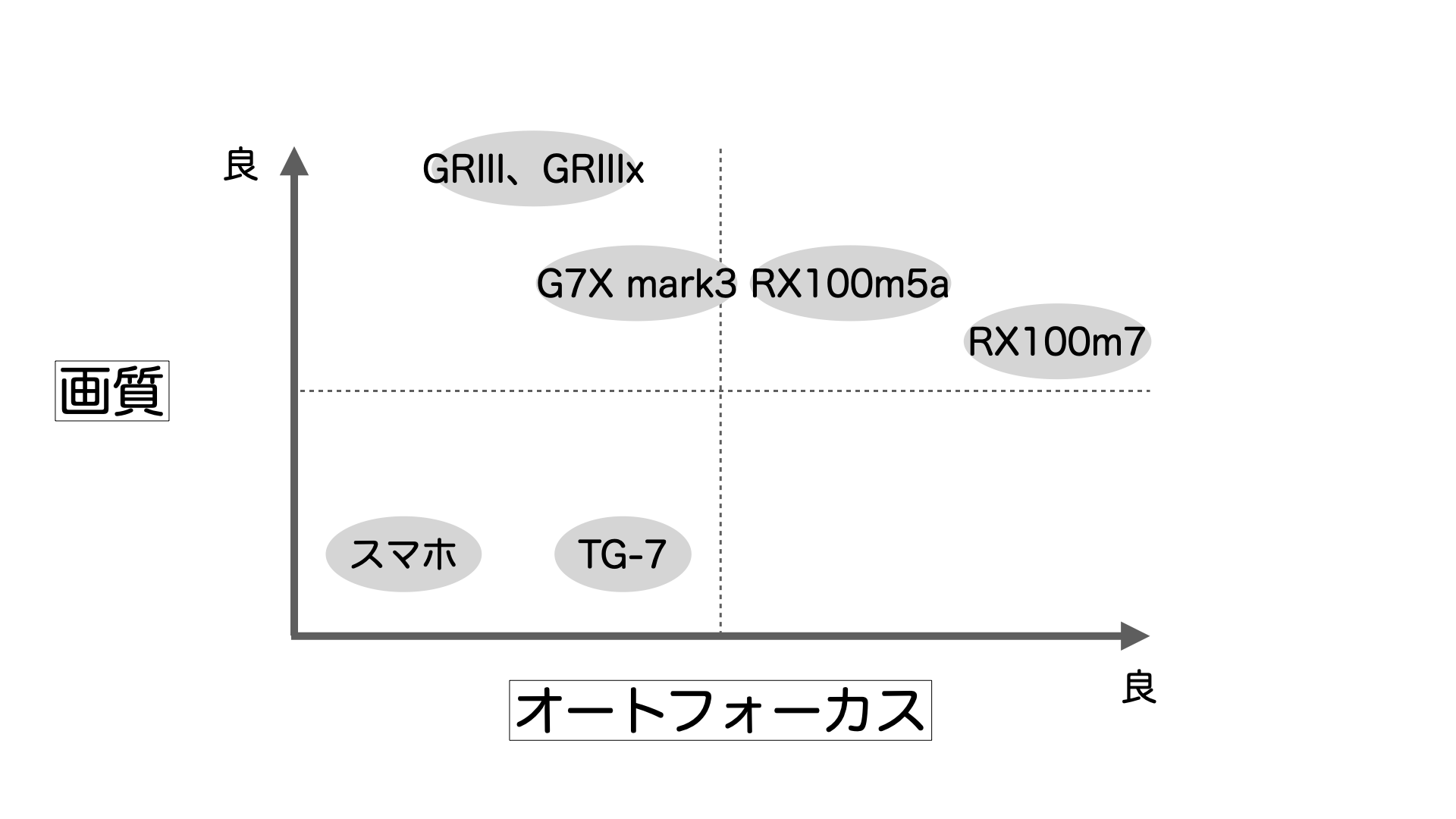
最も画質が良いのは、リコーのGRIIIとGRIIIx。
ソニーRX100m5aとキヤノンG7X mark3が続きます。
オートフォーカス性能は、ソニーのRX100m7がトップ。
次いでソニーRX100m5a。
画質とオートフォーカスのバランスを考えると、ソニーのRX100m5aとRX100m7がベターです。
次に、ズームできる範囲を見ていきましょう。
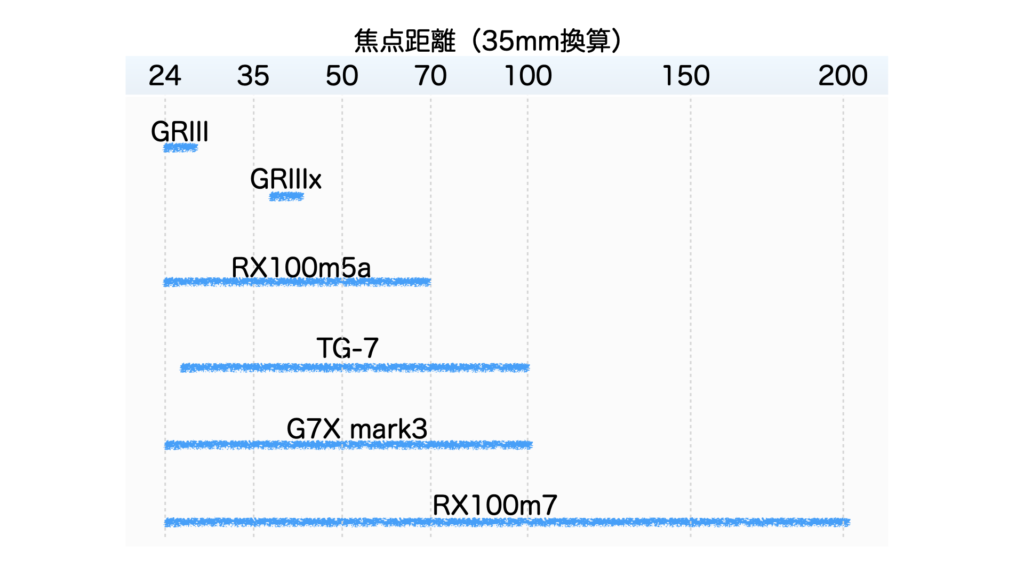
ソニーRX100m7のズーム域は8.3倍と、かなり広い範囲が撮れるます。
対してリコーのGRIII、GRIIIxはズームができません。
便利さを取るなら、RX100m7一択です。
オススメ①|ソニーCyber-shot RX100m7

Cyber-shot RX100m7は、2019年にソニーから発売されたRX100シリーズの最新作。
画質、ズーム倍率、オートフォーカス。どれをとってもハイレベルなカメラに仕上がっています。
RX100m7の特徴
- コンデジとしては大きめの1インチセンサーを採用し、十分な画質を確保
- 24-200mm(35mm換算)の8.3倍ズームにより、日常の9割以上をカバー
- 圧倒的なオートフォーカス性能(α9と同等の性能)
- ポップアップ式のファインダーを搭載
- 180°チルトモニターにより自撮りにも対応
RX100m7の一押しポイントは、圧倒的なオートフォーカス性能です。
ソニーの動体向けミラーレスカメラα9と、同等のオートフォーカス性能を実現。
私は、RX100m7、α9の両方を使用していますが、オートフォーカス性能は同じと言っても過言ではありません。
ポップアップ式のファインダーに自撮り可能なチルトモニター、24-200mm(35mm換算)の高倍率ズームと、贅沢仕様。
最先端の技術を小型ボディに押し込んだ、正にソニーらしい1台です。
高価ではありますが、その価格に見合う価値があります。
 ゆゆねこ
ゆゆねこRX100m7は本当に便利なカメラ。
それは、3年間愛用した今でも変わりません。
- カメラ1台で何でも撮りたい人
- 動体撮影をする人
- 小さい子供を持つ人(幼稚園の運動会までならRX100m7で必要十分)
RX100m7のレビューは、こちら。


RX100m7の作例
私が撮影したRX100m7の作例を紹介します。






オススメ②|ソニーCyber-shot RX100m5a


Cyber-shot RX100m5aは、2016年にソニーから発売されたRX100m5を小改良したモデル。
2018年に販売を開始しました。
ズーム倍率は2.9倍と若干控えめではありますが、画質は優秀。
今回紹介するオススメコンデジの中では、RX100m7に次ぐオートフォーカス性能を誇ります。
RX100m5aの特徴
- コンデジとしては大きめの1インチセンサーを採用し、十分な画質を確保
- 24-70mm(35mm換算)の優秀なレンズによる、優れた画質(公式でMTF曲線を公開)
- 位相差オートフォーカスの採用により、動体撮影も可能
- ポップアップ式のファインダーを搭載
- 180°チルトモニターにより自撮りにも対応
RX100m5aの一押しポイントは、高画質とオートフォーカス性能の共存。
ズーム倍率を2.9倍に抑えることで、最新機種RX100m7よりも高画質。
また、開放F値もF1.8-2.8と明るいため、暗所にも強いカメラに仕上がっています。
位相差オートフォーカスの採用により、オートフォーカス性能もしっかり確保。
利便性やオートフォーカス性能等、最新のRX100m7に一歩譲る点もありますが、画質はRX100m5aが一枚上手。
高画質かつ動体も撮影したいという方は、RX100m5aがオススメです。



私はRX100m5(小改良前のモデル)を使っていたよ。画質はRX100m7よりも優秀!



タッチパネルには対応していないので、注意してね
- ズーム倍率よりも、画質を優先したい人
- 画質を維持しつつ、動体撮影もしたい人
RX100m5(m5A)のレビューはこちら。


RX100シリーズの違いについて、詳しく知りたい方はこちら。


RX100m5(RX100m5aの小改良前モデル)の作例
RX100m5の作例を紹介します。
RX100m5は、RX100m5aとレンズやセンサーは共通。
そのため、画質は同等と考えてOKです。
作例は、私自身が撮影しました。






オススメ③|キヤノンPowerShot G7X mark3
PowerShot G7X mark3は、2019年にキヤノンから発売されたG7Xシリーズの最新作。
24-100mm(35mm換算)の4.2倍ズームに、開放F値1.8-2.8の大口径レンズを兼ね備える。
使い勝手の良いレンズで、動体撮影をしないならば、1インチコンデジの最適解と言うべきカメラです。
G7X mark3の特徴
- コンデジとしては大きめの1インチセンサーを採用し、十分な画質を確保
- 24-100mm(35mm換算)の使い勝手の良い4.2倍ズーム
- 開放F値F1.8-2.8の大口径レンズにより、暗所の画質も良好
- 180°チルトモニターにより自撮りにも対応
G7X mark3の一押しポイントは、使い勝手の良いズーム域と暗所画質の両立。
開放F値はRX100m5aと同様のF1.8-2.8ですが、同じ焦点距離で比べた場合のF値は、G7X mark3に軍配があがります。
つまり、RX100m5aよりも暗所の画質に強いと言うこと。
更に、G7X mark3は100mm(35mm換算)までズーム可能なのは心強い。
使い勝手を確保しつつ、暗所の画質にも有利なG7X mark3。
動体撮影をしないのなら、G7X mark3は最もオススメなコンデジです。



G7X mark2(レンズ性能はmark3同等)を使用していましたが、4.2倍のズームは本当に便利でした。
望遠側の画質はRX100m5よりも優秀です。
- 高画質かつ便利なズーム倍率を求める人
- 室内撮影が多い人
- 動体撮影をしない人
G7X mark2の作例(G7X mark3の前モデル)
G7X mark3の前モデルである、G7X mark2の作例を紹介します。
G7X mark2とG7X mark3は、レンズが共通。
そのため、画質の傾向を掴むことができると思います。
作例は、私自身が撮影しています。








オススメ④|OM SYSTEM TG-7


TG-7は2023年にOM SYSTEM(旧オリンパス)から発売された、防水・対衝撃カメラの最新作。
ズームレンジは使い勝手のいい25-100mm(35mm換算)の4倍ズーム。
水深15mの防水、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃と、タフ性能に力を入れた1台です。
TG-7の特徴
- 防水コンデジとしては大口径のF2-4.9の大口径レンズを搭載
- 使い勝手の良い25-100mm(35mm換算)の4倍ズームレンズ
- 防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃と頑丈
- マクロ機能|顕微鏡モード搭載
- ダイビング撮影向けの純正アクセサリーあり
TG-7の一押しポイントは、他のコンデジにはない圧倒的なタフさ。
上の特徴を見ていただければ分かる通り、とにかくタフ。
水中撮影はもちろんの事、落としても、乗っても大丈夫。
大口径の4倍ズームを搭載し、防水コンデジとしては画質にも拘っています。
センサーサイズが1/2.3インチと小さいため、画質面では不利ですが、それを逆手にとったマクロ機能の優秀さには拍手を送りたい。
ホント、顕微鏡で見てるかの様な写真が撮れます。
また、水中撮影向けの純正アクセサリー類が多いのも嬉しいポイントです。
タフさこそ正義。アクティブに活動するあなたには、TG-7がオススメです。



1世代前のTG-6は、娘用として活躍中。
そろそろ5年目に突入ですが、1度も故障していません。
- フィールドを選ばずに撮影したい人
- 子供用カメラ(子供はカメラを落とすので)
- 充実したマクロ機能を活用したい人
TG-7と同等の性能(レンズ、センサー、タフ性能)を持つ、TG-6のレビューはこちら。


TG-6の作例(TG-7の前モデル)
TG-7の前モデル、TG-6の作例を紹介します。
TG-6とTG-7は、センサーもレンズも共通。
そのため、画質も同等と考えてOKです。










オススメ⑤|リコー GRIII、GRIIIx


GRIIIは2019年にリコーから発売されたGRシリーズの最新作。
フイルムカメラの時代から続く伝統的なデザインは、一目見ただけでGRと分かるフォルム。
焦点距離28mm(35mm換算)、開放F値2.8の単焦点レンズにAPS-Cの組み合わせでありながら、重さはたったの257g。
2021年には焦点距離40mm(35mm換算)のGRIIIxがラインナップに追加されました。
GRIII、GRIIIxの特徴
- APS-Cサイズの大型センサーを搭載し、他とは一線を画す画質
- ズームはできないものの、28mmタイプ 、40mmタイプの2種類のカメラを用意
- 見ただけで分かるGRの伝統的フォルム
- スナップ撮影に特化した機能万歳
GRIII、GRIIIxの一押しポイントは、圧倒的な画質。
ズームはできませんが、その分、画質は他のカメラを寄せ付けません。
高画質を維持しながらも、重さは257g(GRIIIxは262g)。この軽量さは驚異的です。
オートフォーカスは若干苦手ですが、そんな事は気にならないほど画質が良い。
また、起動時間が非常に短く、電源を押した瞬間に撮影できる点も素晴らしいです。
GRIII、GRIIIxには他のカメラにはない、スナップ撮影に特化した機能があります。
その機能の1つのスナップモードは、設定した距離にピントを合わせるモード。
選択できる距離は、1m / 1.5m / 2m / 2.5m / 5m / ∞ 。
予め設定しておくことで、電源を入れてシャッターを押せば、指定した距離にピントが合います。
電源を切っても、設定が記憶されているため、スナップに最適なカメラです。
ゾーンフォーカスの考え方を活用できると、よりスナップが捗ります。
F値と、ピントを合わせる距離によって、m〜mまではピントが合ったように見えるフォーカス範囲
【例】F値5.6でピントの設定距離を5mに設定すると、2m〜 ∞までピントが合ったように見える
ズームを捨てて、画質に全振りしたカメラ。
画質こそが全て。
GRIII、GRIIIxは、スマホとは別次元の画質を手に入れたい方にオススメです。



GRIIIはしばらく使用していましたが、本当に画質がいい!
ただ、オートフォーカスは苦手なので、そこは注意だよ。



アップデートで瞳オートフォーカス機能が搭載されたけど、私の期待には届きませんでした。
- ズームは不要。とにかく高画質な写真が撮りたい人
- スナップを撮る人(ゾーンフォーカスが活かせる人)
GRIIIの作例
私がGRIIIで撮影した作例を紹介します。




まとめ
今回紹介したコンデジは、スマホやミラーレスカメラとは一味違った魅力を持つカメラばかりです。
是非、自分に合うコンデジを選んでみてください。
きっと、写真ライフがもっと楽しくなりますよ。
- ソニー Cyber-shot RX100m7
- ソニー Cyber-shot RX100m5a
- キヤノン PowerShot G7X mark3
- OM SYSTEM(旧オリンパス) TG-7
- リコー GRIII
- リコー GRIIIx


















コメント